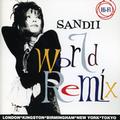カレンダー
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025/10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
最近の記事
最近のコメント
- もしかして福岡さん?え〜嘘、ほんとう… (手帳)
- まだです。スピーカーセッティングのた… (福)
- アナログ・レコードは
試したのです… (松島玉三郎) - 先日はお忙しいところありがとうござい… (さる)
- ソケースロックのサイトが引っ越してい… (福)
- 行けなくて残念です。
早く聴きに行… (かたおかいくお) - 「おかめDEナイト」チケットほぼ完売… (リイズルイスT)
- あー、そいえばマン2の前あたりでふた… (いけ)
- 楠です。スネアは足りてますか? (XNOX クスノキス)
- きのう、三宮で「TSUNAMI」を歌… (青木)
月別アーカイヴ
カテゴリー
Blogを公開している友人
- piki
- hanmamama
- hitomisings4u
- a
- papas
- xnox
- ikuokataoka
- pue
- biscuitmusic
- ammuff
- bzowskip
- ike
- mal
- suzukikeiichi
- kichop
- nt
公開所属グループ
プロフィール

a person powered by ototoy blog
recommuni四方山話記事リスト 43ページ目
自転車通勤
今日は2回目の自転車通勤。世田谷の自宅から南麻布の事務所まで約40分。東京西部から都心に向かうとどういうルートでも環六あたりに上り坂がある。そこだけしんどいのだが、あとは快適だ。そんなに疲れないし、電車+徒歩で行くより時間はかからない。
さらに夜高円寺で打ち合わせがあったので、南麻布から高円寺へ。これはさすがに1時間かかった。途中で猛烈におなかがすいたので、コンビニであんパンを買い食い。自転車移動はこういう寄り道も手軽でよい。
高円寺から自宅へは30分弱だった。
かなりの運動量だな。やせるかな?
四方山話その百【続・楽譜】
音楽と楽譜についてのエピソード、もうひとつ。と言っても前回と同じ類の話だけれど。
遊佐未森のレコーディングをアイリッシュ系のミュージシャンといっしょにやったときのこと。“Nightnoise”というバンドで、伝手はなかったけど飛び込みでアプローチしたらOKしてくれた。さあ、初めてアイルランドへ行くぞ、と意気込んだら、彼らはそのときアメリカのオレゴンに住んでいた。
場所の話は今回は置いておく。ともかく日本人は遊佐本人だけで、あとは全部彼らと作ろうという企画だったので、曲とだいたいの構成は考えていくが、アレンジと演奏は現地で一からスタート。ということで、まずは入念なリハーサルを行った。
“Nightnoise”はアイリッシュの伝統音楽をベースにしながらも、ポップでコンテンポラリーな要素を取り入れた、インストゥルメンタル中心のバンド。変拍子なども随所に現れるかなり複雑な演奏を、すごいグルーブで聴かせてくれるので、譜面バリバリの人たちだと勝手に思っていた。
だって日本人だと、変拍子に強い人はまず間違いなく譜面にも強いから。だが、やはり、アイリッシュ・ピーポーも譜面はダメだった。コードと進み方だけを書いた簡単な楽譜を用意していったのだが、全然慣れてない様子。ピアノがトゥリーナ、ギターがミホール、フルート&パイプにブライアン、フィドル(バイオリン)はジョン・カニンガムというメンバーだが、ジャズを勉強したというブライアンとプロデューサーでもある(その後すごく活躍したが2003年に惜しくも他界)ジョンが多少解る、という程度。
なので初めのうちは、8ビートのシンプルな曲もなかなかうまくいかない彼らだったが、リハの合間に自分たちの曲をやってもらうと、いきなりノリが豹変する。ほんとすごい。つまり彼らは変拍子やなんかも、特に意識してやっているワケではなく、自然に、そして必要だからそうしているだけなのだ。それが変拍子だということには無関心というか、拍子なんか関係ないのだ。
そもそも「変拍子」という言葉が楽譜発想だね。4拍子や3拍子が普通だという考え方があるからそれ以外の拍子が「変」ということになる。でも感覚でやっている人たちには、それが感覚的に正しければ、全然「変」じゃない。
後にアイルランドのダブリンにも行ったが、かの地ではほんと、音楽が空気のように街にあふれている。パブに入ると必ずアイリッシュ(ケルト)・ミュージックを演奏している人たちがいる。老人もいれば若者もいる。日本ならそのへんの赤ちょうちんで、客が三味線や笛で民謡を演奏しているようなもんだが、そんな場面はまずありえないよね。
彼らにとって楽器演奏は、だから、親や兄弟などとの生活の中で、自然に覚えていくものなのではないだろうか。理屈ではなく、料理や手仕事のように見よう見まねで。
昨今の(日本の)アマチュア・バンド諸君は、曲をコピーするのに、楽譜を買ってきてそれを見ながらやるそうだ。だから楽譜が出版されていない曲はできない、とか言ってる。ボクも学生時代にバンドをやっていたけど、ひたすら耳コピーだった(楽譜がそんなに売られてなかったからだけかもしれないが)。何度も何度も聴いて、どうやって演奏しているのかを自分で発見していくところに、喜びと上達が生まれると思うんだけどな。
譜面じゃなく感覚で生み出された音楽を、譜面を見ながら練習する日本人、というこの図式はいったいどうなんだろう?
2005.05.15
福岡智彦
カリフォルニア・ナイト
昨夜は、北中さんと天辰さんの“シルバー・クリケッツ”+ZEPPの藤井君のDJイベント「カリフォルニア・ナイト vol.8」に行った。渋谷の「ツインズよしはし」。ここは少々音がライブ過ぎるのを除けば、居心地のよい場所で好きなんだけど、なんと今月いっぱいで閉店するのだという。
懐かしい顔がいっぱいだった。いきなり和田博巳さんがいた。最近は(というかもう10年くらいっておっしゃってたが)オーディオ評論家をやってらっしゃるそうだ。
今ポニーキャニオンにいらっしゃる高橋ユージさん、SMEの北川さん、元ユニバーサルの内田さん、音楽ライターの山本智史さん、元どこだっけ?今JVCネットワークの粕谷さん、ソニーマガジンズの皆川君…
途中ですなちゃんも登場。さっそく山本さんが主催するという9/3、4の狭山でのイベントに、初対面なのに「私は呼んでくれないんですか?」と迫る。困っている山本さんを尻目に、これも初対面の和田さんを説得し、なんと和田さんのベースにすなちゃんのおしゃべりで、コンビを結成するかなんて話になっている!
ゲストDJが元ミュージックライフの赤尾美香さん。なかなかナイスな選曲でした。
いい音楽をサカナにいい人たちと楽しいひととき。
四方山話その九十九【楽譜】
ドラムをやっていたから、リズムはだいたい読めても、音階はぜんぜん。楽譜を見てすぐ弾ける、これを「初見が利く」というが、そういうのを見るとすごいなー、と思う。訓練によって、オタマジャクシの位置とその形で、何をどう弾くかという運動神経がすぐさま反応するんだな。
だけど一方、楽譜は読めないけどすごく上手なミュージシャンもいっぱいいる。楽譜なしには考えられないクラシックのミュージシャンは、逆にアドリブが不得意だったり、コードしか書いてないとどうしていいかわからない(むしろコードを知らない)という人もいて、このへんが音楽のおもしろいところでもある。
やはり理屈から入る人が多いのだろうか、日本人だと、特にプロの場合はある程度読めないと仕事にならない、ということもあって、オタマジャクシまで初見ができなくても、コードやリズムや進行くらいはほとんどのミュージシャンが解る。
ところが欧米は違う(他は知らない)。むしろ読める人が少ない。
土屋昌巳さんの担当をしていたころ、彼のレコーディングでロンドンに行ったときの話。
土屋さんは一時JAPAN(バンドだよー)に参加していたくらいだから、そのメンバーたちと仲がよい。ベースのミック・カーンに演奏を頼むことになった。レコーディング予定日の3日くらい前に、ミックにベース抜きのラフミックス・テープを渡す。土屋さんは何も説明しない。「彼は完璧に考えてきますから」と言う。
当日になり、ミックがスタジオに現れた。しばし談笑した後、ベース・ギターをセッティング。「さあ、一度合わせてやってみようか」、エンジニアがマルチ・テープをスタートすると、なんとなんとなんと、曲の頭からおしまいまで、一音のミスもなしに完奏してしまった。しかも譜面も見ず、例の、知ってる人はわかるだろうけど、彼にしか思いつかないようなユニークでかっこいいフレージングで。
「彼は完璧に考えてきますから」という土屋さんの言葉は大げさでも何でもなく、むしろ控えめな表現だった。だって彼は「完璧に考えてきた」だけではなく、さらにそれを「完璧に憶えてきた」のだから。一言の指示も注文もなかったのに、もうその曲にはそれしかないというような、この曲はベース・ラインから作りましたと言っても誰も疑わないような、すばらしいフレーズを、それをもう何度もプレイしてきたような手慣れた指運びで淡々と弾く姿に、ボクはもうまいってしまった。世の中は広い。すごい人がいるわ……。
実はほんとに驚いたのはそのあとなんである。
ある一箇所だけ土屋さんはフレーズを手直ししようと思った。それを彼に伝えるのだが、譜面は読めないみたいなので、フレーズを歌いながらある音を、「Gに変えてくれ」と言った。そうしたらミックは「Gってどこだ?」って聞き返した。
皆さん、ベース・ギターのGはどこかボクでも知ってますよ。それを天下の、JAPANの、男前の、凄腕ベーシストが、Gがどのフレットなのか知らないんですよ!
もちろんバカにして言ってるのではない。
Gがどこか知らないということは、ある音を弾いてもそれをAとかCとかの「言語」にしないということだろう。フレーズを考えるのも、耳と指と記憶だけでやっているのだろうか。そうしてでき上がったフレーズを、曲の構成まで含めて完璧に憶えこむなんて、凡人のボクには、想像もできないくらいたいへんな作業だとしか思えないが、彼の場合、そういうことが得意な脳ミソの構造になっているのかもしれない。
でも、個人の才能ももちろんあるだろうが、そもそも楽譜を使わないで音楽のスキルを高めていくという環境が、日本のような普通に楽譜ありきの環境とは、全く違う音楽の捉え方を育むのかもしれない。ミック・カーンのようなやり方は、向こうではよくあることなのかもしれない(ただ彼ほど完璧なプレイヤーは他に知らないけどね)。
どちらがよい悪いではないけど、やっぱり海外に個性的なミュージシャンが多いのは楽譜という「マニュアル」を使わないからではないだろうか?
2005.05.09
福岡智彦
『赤道小町ドキッ/山下久美子』

山下久美子最初にして最大のシングル・ヒット、かな。あ、ボクについてもそうだ。
(今や経営もたいへんそうな)カネボウの1982年夏のキャンペーン、略して夏キャンのタイアップでした。当時季節ごとに繰り広げられたカネボウと資生堂のキャンペーン合戦は、イメージソング対決でもあったので、タイアップした曲も必ずヒットしました。この「赤道小町ドキッ」はオリコン・チャート最高2位。1位はなんだったんだろう?覚えてないです。それに対する資生堂のイメージソングも覚えてない。ネットで調べたら、その年の春キャンの資生堂タイアップは忌野清志郎&坂本龍一の「い・け・な・いルージュマジック」でした。
作詞、松本隆、作曲、細野晴臣という黄金コンビに、演奏は細野、高橋ユキヒロ、松武秀樹、大村憲司、というYMOマイナス1メンバー!
テクノだけど、ハイハットだけ器械でやらせ、他のドラムは生。スタジオで、やっぱないと叩きにくいんでしょうね、ハイハットにタオルをぐるぐる巻きにして、演奏していたユキヒロさんの姿が今でも目に浮かびます。
『女ひとり/小柳ルミ子』

このころは実によかったのだ、小柳ルミ子さん。
ポップスでなく和風路線で、でも決して演歌ではなく、って今じゃちょっとない独特のキャラクターでした。
そんな彼女が日本の抒情歌を歌ったアルバムに収録されている、デューク・エイセスでおなじみの名曲です。
この時代の歌謡曲はおもしろかった。
『フォー・ザ・モーメント/HIRTH MARTINEZ』

このゆったり感!ほっとしますねー。
このアーティストよく知らないんですが、Dreamsvilleのサイトで見ると、すごい豪華なレコーディング・メンバーです。
[参加ミュージシャン]
ロン・カーター(アコースティック・ベース)
ウィル・リー(ベース)
リンカ−ン・ゴーインズ(ベース)
ヴァンデレイ・ペレイラ(ドラムス)
ガース・ハドソン(アコーデイオン/テナ−・サックス/ピアノ)
デビッド・サンボーン(アルト・サックス)
ランディ・ブレッカー(トランペット)
ディエゴ・アルコラ(トランペット)
コーネリアス・バンパス(テナー&ソプラノ・サックス/フルート)
ボブ・マグヌッソン(クラリネット/ベース・クラリネット)
ジェニー・マルダー(ハーモニー・ヴォ−カル)〜マリア・マルダ−の娘
ジョン・サイモン(ピアノ/ハーモニウム)
ハース・マルティネス〜ヴォーカル&ギター(全曲)
[レコーディング]
1998年8月、ニューヨークのシア・サウンド・スタジオにて
[エンジニア]
ノア・エヴァンス〜ギル・エヴァンスの息子
『バスルームから愛をこめて/山下久美子』

自分の日記にも書いたけど、私の音楽ディレクター仕事、第1作です。
サビのコーラスを、デビュー前のシャネルズ(後のラッツアンドスター)にお願いしたくて、リーダーの鈴木(いわゆるマーチンさんですね)と電話で話したら、「俺たち譜面とか読めないし、そんなうまくないから…」とかいう理由で断られたので、実際唄っているのは「タイム・ファイブ」というグループです。
久美子がデビューするころにはシャネルズはもうデビューしてすぐに売れていて、レコード会社のプロモーションマンが、ラジオ局などにプロモーションするとき「女性版シャネルズって呼ばれてますから」などと言っているのを聞いて、恥ずかしい気分になったことを思い出します。
『ドリーム・キャッチャー (フィアース ソフト サンバ)/Sandii』
四方山話その九十八【歌と声〜体験編】
前回、大瀧詠一さんの「歌と声」についての“学説”を紹介したが、それを書きながらそう言えばと、思い出したことがある。
昔の話である。音楽ディレクターとしてはじめて主体的に関わったのが山下久美子さんだ。大先輩の木崎さんがプロデューサーでいろいろ教えられながらだったが、ともかく、久美子さんもデビュー、作詞の康珍化(かんちんふぁ)氏、作曲の亀井登志夫氏も初のプロ仕事、というチームだったから、みんな若いし、はりきっていて、すごく楽しかったし、いっしょうけんめいだった。
以後敬称略。
久美子はアマチュアでライブハウスなどで歌っていた。渡辺プロダクションと契約し、東京に出てきてからもライブをやっていたから、「歌える」人だと思っていたが、いよいよボーカルの録音になると、意外に苦労した。ライブで歌っていたことが、歌い方に妙なクセをつけていた。どうも口先で歌っている感じで、こじんまりとまとまってしまう。伝わってくるものがない。
ジャズとかブラック・ミュージックを歌っていた人が、「おーとーこーなんてシャボン玉ー」(「バスルームから愛をこめて」)なんて歌うことに抵抗があったのかもしれないが、ボクも新米だから、どうすれば打開できるのかまったくわからない。木崎さんに相談したかどうか忘れてしまったのだが、ともかく「声を出す」ことだけに集中したほうがよいと思い、うまく歌おうとか、詞の意味とか、リズムやピッチも気にしないで、そう、「童謡を歌うように大きく口を開けて歌って」と頼んだ。
久美子はプライドが傷ついたかもしれない。歌が好きで、スカウトされ、それなりに自信もあってこれまでやってきたはずだ。今さら「子供が童謡を歌うように」などと言われたのだから。
でも、彼女はそれで開き直ったというか、ふっきれたのだろう。結果的にはそれを機会に、歌が全然変わった。見違えるように、歌に説得力が増していった。
「歌は声、声は作るもの」というのが大瀧詠一説。ボーカル録音の一週間くらいの間に歌がいきなりうまくなるわけはないだろうが、声の出し方が変わっただけで全然歌が違うものになったのだ。大滝説の正しさを裏づける話ではないだろうか?
こうして録音することができた歌が、デビュー曲の「バスルームから愛をこめて」である。今聴いてもすごくいい歌唱だと思う。
http://recommuni
ボクと山下久美子のタッグは5年間、アルバム7枚で終了するが、それから10年後くらいに、あるクリスマス・パーティで出会った。彼女の声はまた変化していて、低音がしっかりとして、力強さが倍増していた。成長し続けてるなと感心した。その声で、彼女はそのとき、やはり「バスルーム」を歌ってくれた。
2005.05.01
福岡智彦