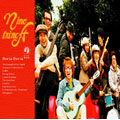カレンダー
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025/10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
最近の記事
最近のコメント
- もしかして福岡さん?え〜嘘、ほんとう… (手帳)
- まだです。スピーカーセッティングのた… (福)
- アナログ・レコードは
試したのです… (松島玉三郎) - 先日はお忙しいところありがとうござい… (さる)
- ソケースロックのサイトが引っ越してい… (福)
- 行けなくて残念です。
早く聴きに行… (かたおかいくお) - 「おかめDEナイト」チケットほぼ完売… (リイズルイスT)
- あー、そいえばマン2の前あたりでふた… (いけ)
- 楠です。スネアは足りてますか? (XNOX クスノキス)
- きのう、三宮で「TSUNAMI」を歌… (青木)
月別アーカイヴ
カテゴリー
Blogを公開している友人
- piki
- hanmamama
- hitomisings4u
- a
- papas
- xnox
- ikuokataoka
- pue
- biscuitmusic
- ammuff
- bzowskip
- ike
- mal
- suzukikeiichi
- kichop
- nt
公開所属グループ
プロフィール

a person powered by ototoy blog
recommuni四方山話記事リスト 27ページ目
『The Crow/浜田真理子』
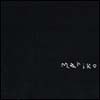
最初に聴いたのはずいぶん前(2001年)だが、軽く歌っているようなのにすごく存在感があって、きれいな英語なんで日本人と思わなかった。
で、地方に住んでいて(松江)、活動もしてなくて謎につつまれた存在だった。
発売2002年とあるが、最初は1998年に自主で500枚だけ作ったのだそうだ。それが伝わって、評判を呼び、再発されたのだ。ほんとによい音楽は不滅なのだね。
『Blessed Be/Kris Miller』
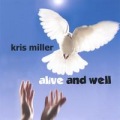
何度か聴いてるうちにすっかりはまってしまいました。
イントロ〜Aメロのブルージーな感じと、裏腹に妙に明るいサビに交互に攻められて、だんだん頭がグニャグニャしてきます……。
「歴史的迷曲!!」という評価があれば一票を投じたい。
WBC
テレビでWBCの決勝戦を観た。優勝おめでとう!
考えてみたらテレビで野球の試合を最初から最後まで観るなんて何年ぶりだろう?
面白い試合だったけど、やっぱ4時間はちと長いなー。
サッカーとかマラソンとか2時間強で、ちょうどいいんだけどね。ドライブも2時間走ったら休憩をとりなさいって言うしね。
この長さも最近の野球人気の低迷に関係してるんじゃないかな?
5回くらいでおしまいにしたらどうだろ?
『L'Auto Inglese/nino trinca』
『Going Home/nino trinca』
『王様とギロチン/nino trinca』
『The Benefit of Mr.Tight/nino trinca』
『サルビアの花/イズミカワソラ』
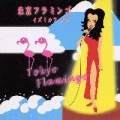
昨日この曲の話をしていたので、レコメンド。
早川義夫さんの名曲だけど、調べたら、詞は早川さんじゃないのね。
で、このバージョンはフランス語?
独特のふんいきを持った人ですねー、ソラさん。
おもしろいし、とても魅力的です。
酒の手帳を楽しむ会
ボクが芋焼酎を好きになるきっかけとなったのが「酒の手帳」という焼酎。
10年前、博多に仕事で行ったとき、地元の知人が「面白い呑み屋に行きましょう」と言うのでついていくと、やがて神社に入っていく。抜け道?、と思ったらなんと、その神社の一角に、荻本さんというおっちゃんの呑み屋があった。呑み屋と言っても神社の社務所の台所みたいなところで、看板も何もない。教えてもらわないと絶対にわからない。
酒はただ一種類、「酒の手帳」というそのおっちゃんが作った芋焼酎。しかもお湯割りで呑め、との厳命。どちらかという蒸し暑い夜だったと思うが、ロックや水割りは許してくれない。当時は今のような焼酎ブームのカケラもなく、大ワインブームだったし、ボクは学生時代に日本酒と間違えて薩摩白波を少し呑んで、臭いというかなんと言うか、コリゴリした経験以来、そのときまで芋焼酎は敬遠していた。で、なんの期待もなく、というかむしろ恐々、その「酒の手帳」のお湯割を呑んだら、そのうまいこと!
しかも、すでにビールやら何やらけっこう呑んで酔っ払っていたのだが、「酒の手帳」のグラスを重ねていくうちに、酔ってることは酔ってるんだが、なんだか頭の芯がすっきりしてくるようで、それは酒を呑むことでかつて味わったことのない不思議な感覚だった。つまみも全部おっちゃんの手作りで、自然のものばかり、うまくて身体にやさしい。実に心地よい数時間を過ごした。
それからいつ始まったのか、たまーに、おっちゃんが「酒の手帳」と手作りお惣菜を持って東京で「酒の手帳を楽しむ会」を催してくれるようになった。日曜の昼間っからゆっくり呑み、食べ、語るという楽しい会だったが、なんせ九州から東京にクルマで来る(おっちゃんが一人で運転してくる)のはたいへんだ。いつのまにか、世の中大焼酎ブーム、しかもメインは芋、となり、ちょっとした呑み屋なら芋焼酎の何種類かは置いていてあたりまえ、という時代になったが、なぜか「酒の手帳」はその波に乗れず(乗らず?)、おっちゃんもあまり儲かってないので、ここ2年ばかりは開催されず、地元福岡では月一回やってるのだが、東京ではもうやれないという話だった。
それが、昨日(2006年3月12日)久々に開催された。「もうやれない」と言ってたおっちゃんをやる気にさせたのが、埼玉と横浜に「酒の手帳」をブログで絶賛している人がいたことだったと言う。
だけど、声をかけた友人たちがほとんど参加できず、動員が少なくてまたこれが最後ということになってしまうかもなと思いつつ、行ってみると案外たくさん集まって、30人くらいはいたかな。場所は大田区産業プラザという施設の和室。畳というのが、リラックスできて、実にまたよいね。知らない人ばかりなんだけど、呑んでるうちにいろいろおしゃべりして知り合いになっていく。
紹介された埼玉の人は「ただの呑んべです」って笑ってたが、横浜の人は「横浜焼酎委員会」(!)の人。毎月うまい焼酎の試飲会をやってるそうで、そこに「酒の手帳」をぜひ加えたい、とのことだ。
「横浜焼酎委員会」サイト→ http://www
さらに鹿児島料理のお店をやってる人がいたようで、そこが日曜は定休なので場所を提供してくださるという話もあり、また10月にやりましょう、という宣言が出された。よかったよかった。
ほんとにいいものはちゃんと伝えなくちゃね。ブームになってほしくはないけど。
電気用品安全法その後
2/18の日記で、署名協力をお願いしましたが、
http://recommuni
高橋健太郎さんのブログとか読むと、問題は単純ではないようです。
http://blog
(署名受付はもう終わっていますが)
原因はJSPA(日本シンセサイザー・プログラマー協会)の「電気用品安全法に関する活動方針」
https://www
の、
「この方針は電子楽器を扱う専門家の立場から、本法が音楽発展の妨げにならない措置を請願するものです。本法の本施行に反対し法律改正などを求めるものではありません。」
という一節ですね。
健太郎さんの意見は、この法律そのものが酷いのだから、お目こぼし的発想ではダメだ、ということだと思います。
ナショナルの事件などもあり、安全はもちろんだいじなことですが、この法律については矛盾だらけの内容の上、与える影響が大きい、そこが問題なんですね。とても健太郎さんのように調べたり書いたりできないので、また彼のブログを参照させていただきます。